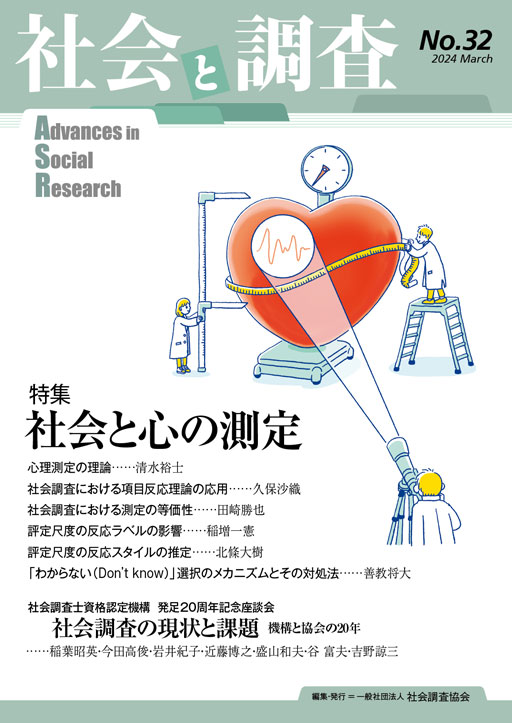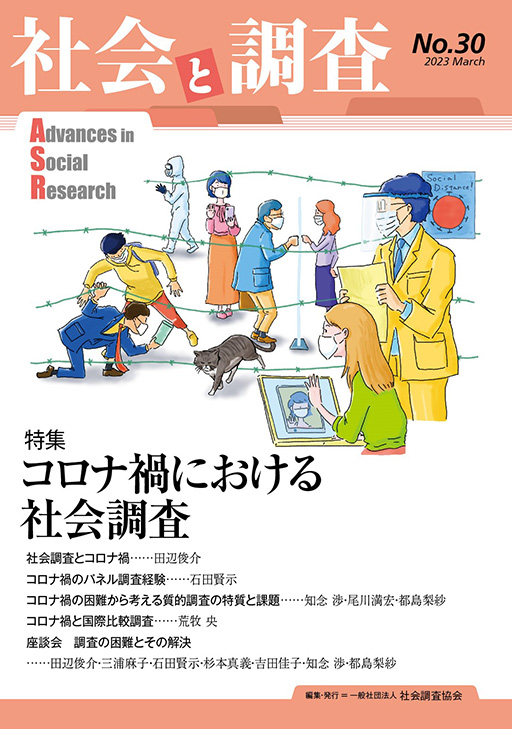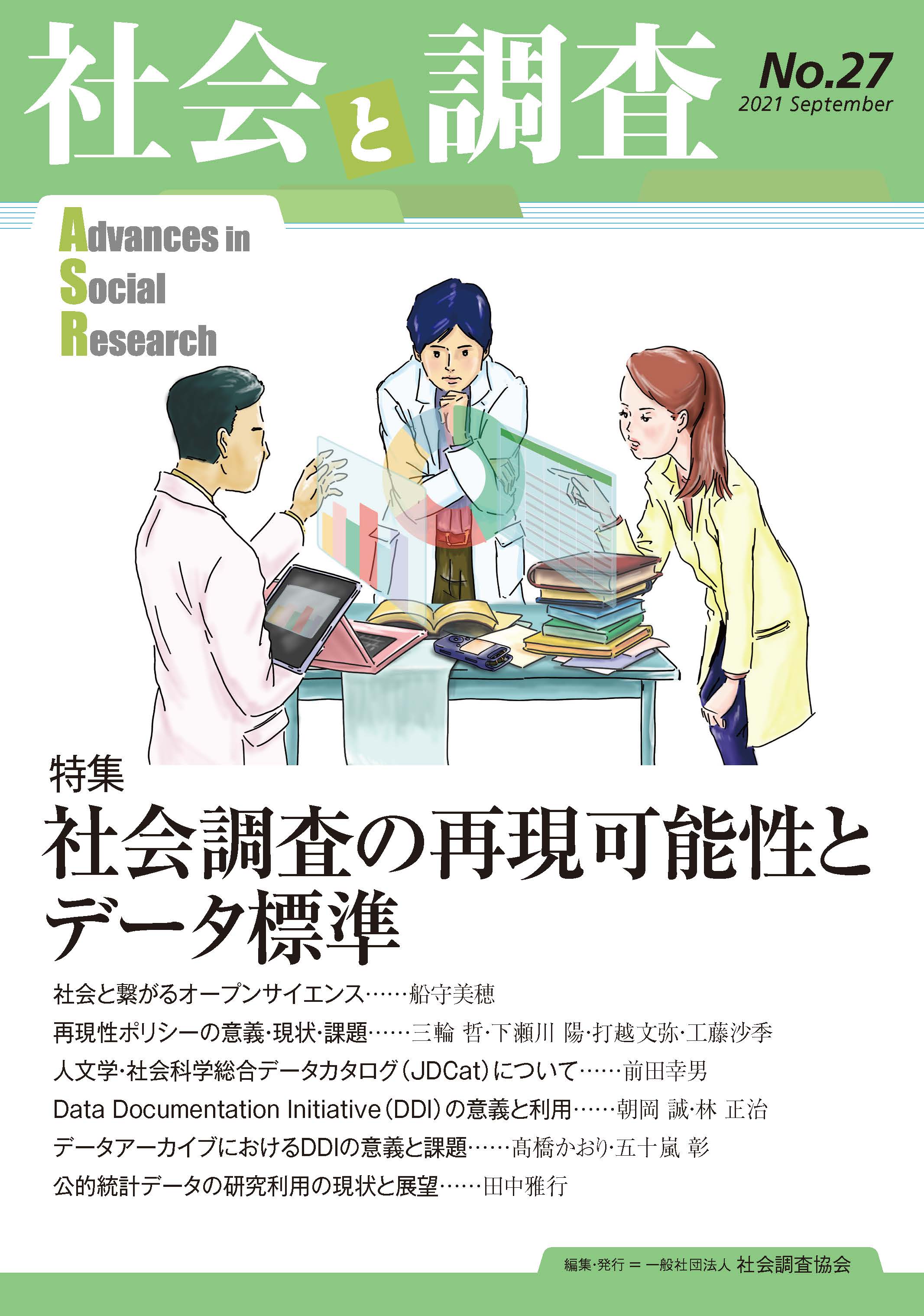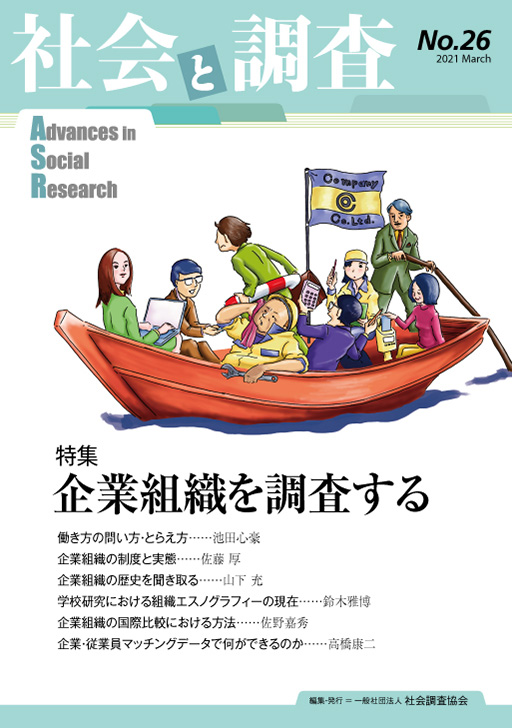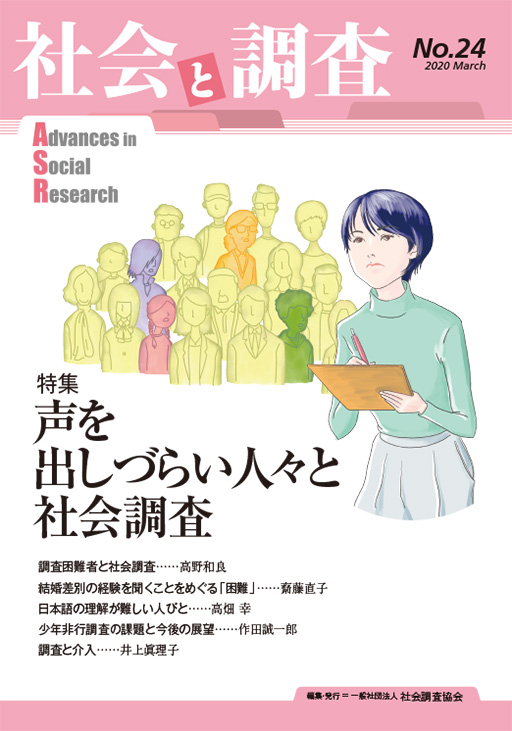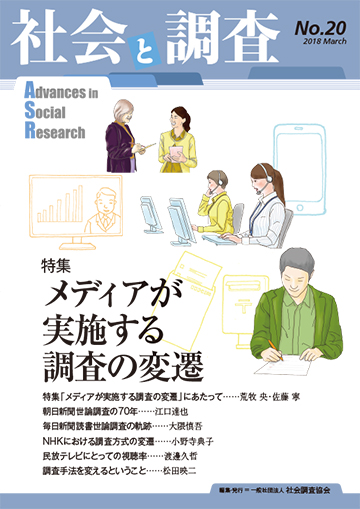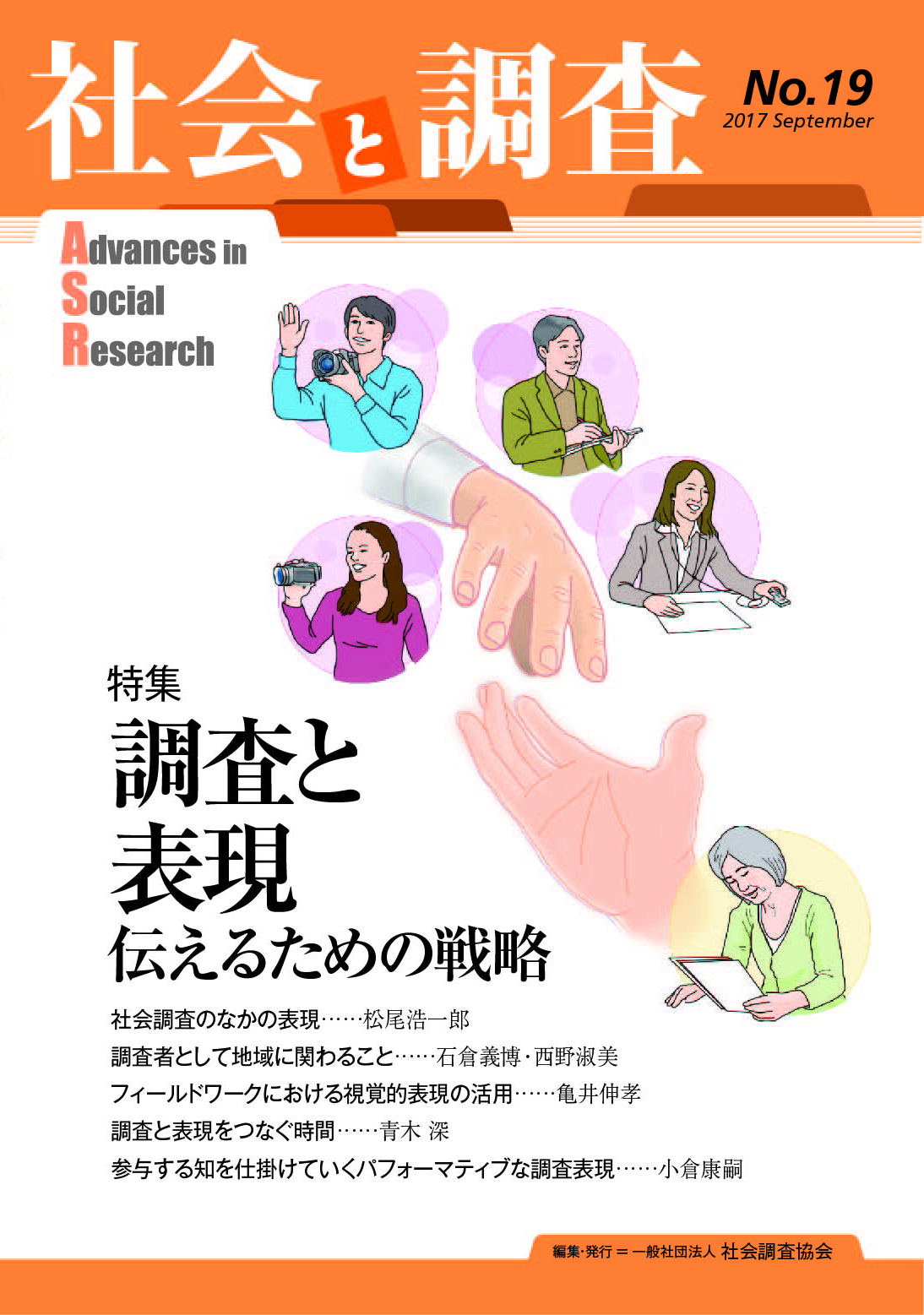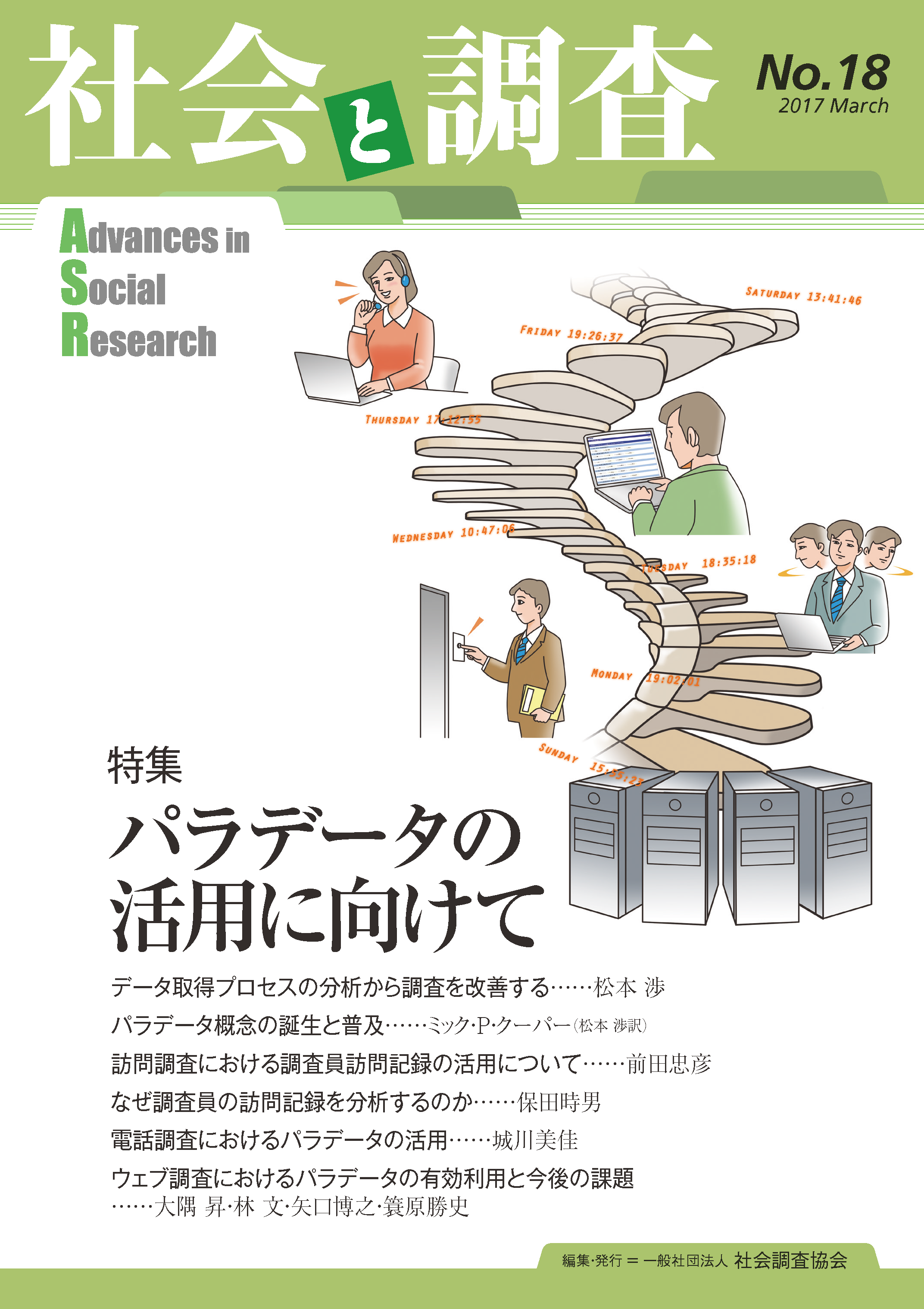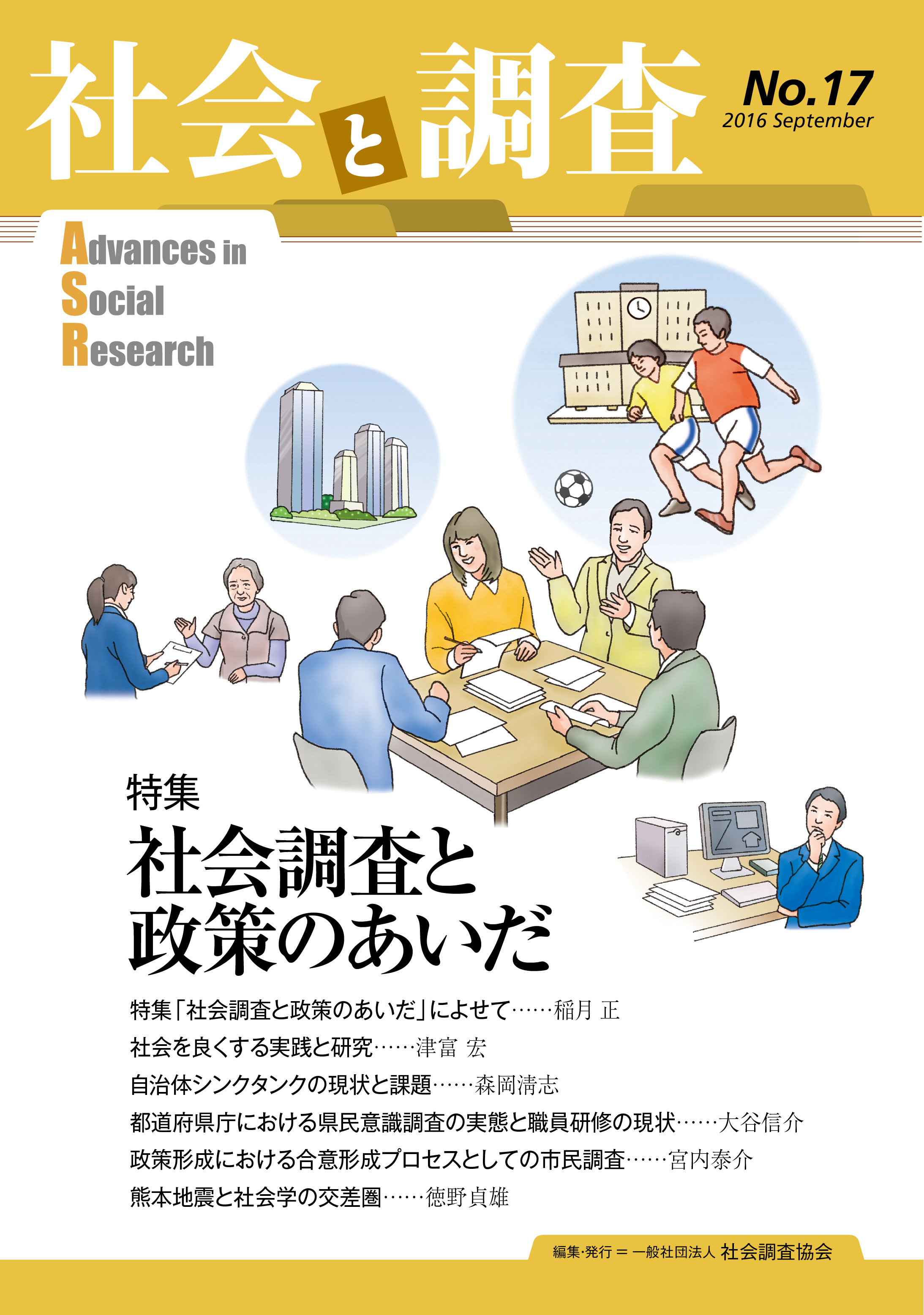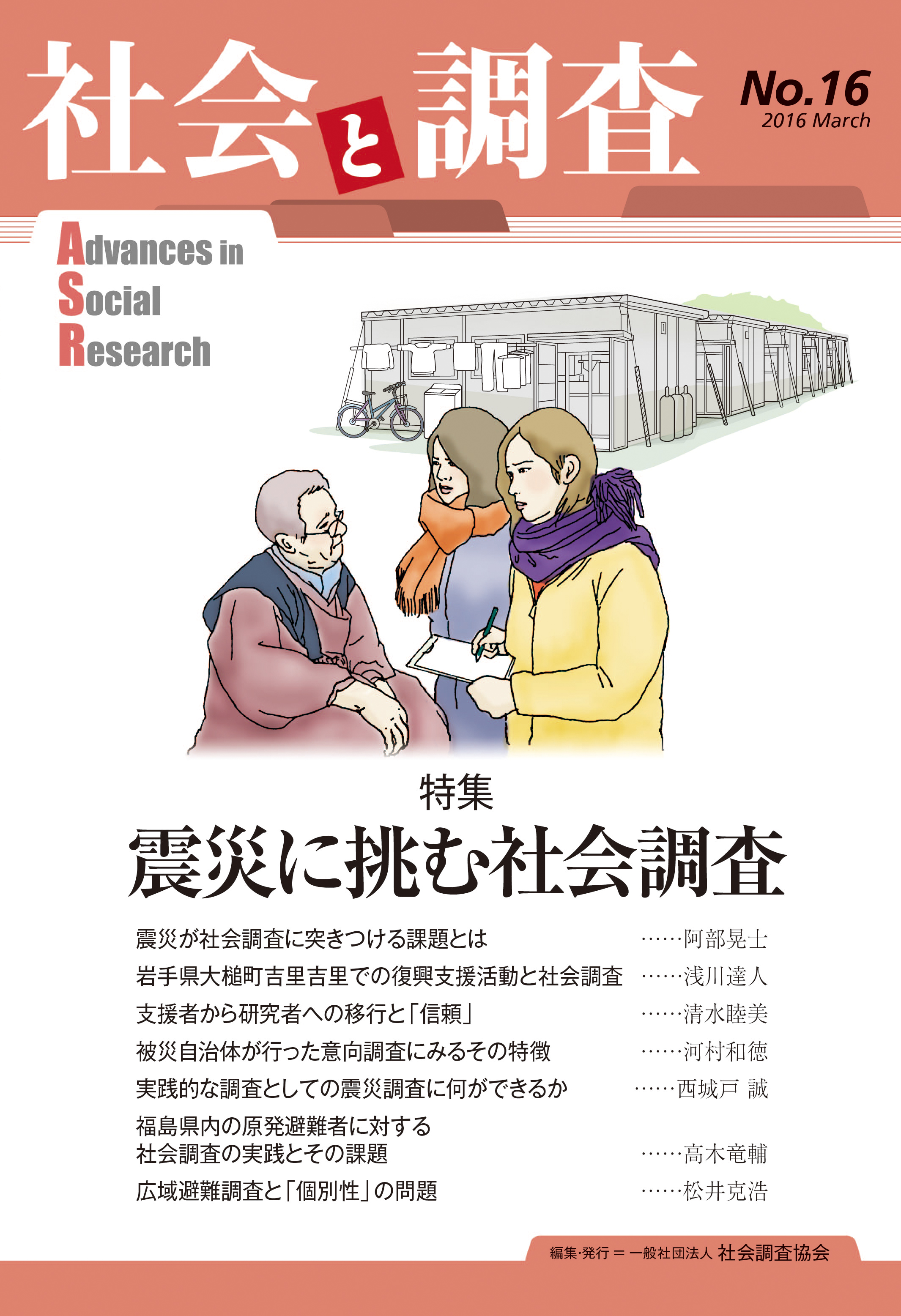社会と調査
的確に社会を読みとり、課題に挑む
社会調査協会 機関誌

本誌は有斐閣アカデミアの制作・販売でしたが、2016年3月に京都通信社が引き継ぎました。各号の販売はもちろん、定期購読も受けつけております。お申し込みは、弊社メールアドレスもしくはFAXまでお願いいたします。
定期購読のお申し込み先はこちら
社会調査における測定の関心はさまざまであるが,大きく分けて「社会の測定」と「心の測定」という2つの目的があるだろう。社会学者や政治学者は,社会意識などの集合的な特徴の記述を目的とし,(社会)心理学者は回答している個人の心理状態の推定を目的としていることが多い。どちらの目的であっても自己評定式の尺度を用いていることから,正確に測定するためのテクニックには共通するものも多い。
本特集は,心理測定学,社会心理学,政治心理学の分野における「社会と心の測定」について詳しい6名の研究者が執筆を担当し,社会調査に役立つさまざまな理論と方法を紹介する。具体的には,心理測定の理論の紹介,社会比較を行うための方法,リッカート形式の尺度において生じうる反応バイアスの問題やDK回答への処理などについてである。本特集論文はどれも,量的な社会調査にたずさわる人に役立つ内容であり,ぜひ活用していただきたい。
清水裕士「特集紹介」から抜粋
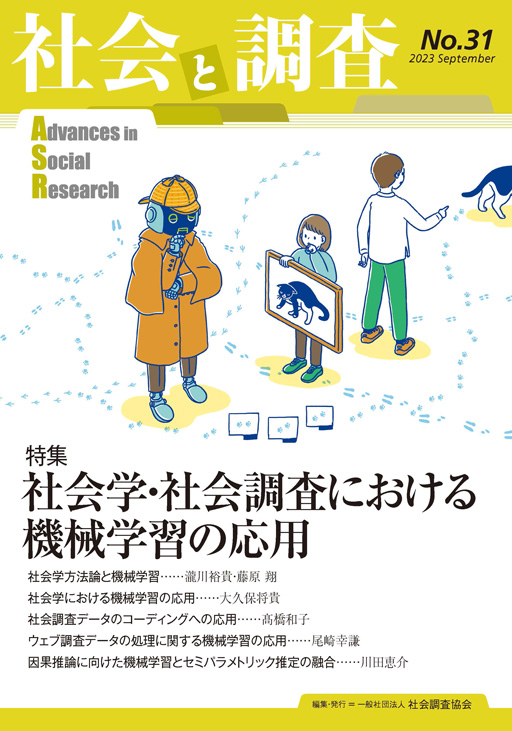
社会と調査 第31号
特集
社会学・社会調査における機械学習の応用
- 2023年9月発行
- 編集・発行 社会調査協会
- B5判 112ページ
- 定価 1,200円+税
- ISBN 978-4-903473-43-7
今、機械学習が社会学やその隣接領域できわめて大きな注目を集めている。機械学習は情報技術の拡大とともに急速に発展し続けている分野である。社会学でも以前から機械学習への関心はあったけれども、主として、ビッグデータやテキストデータなど、従来の社会学では扱わないデータの解析手法として理解されてきたように思う。もちろん、ビッグデータやテキストデータは機械学習の主たる応用先の一つであり、社会学にとってそうしたデータの重要性も高まりつつある。しかし近年の機械学習の広がりはそれにとどまらない。サーベイ調査をはじめ多くの社会学者や社会調査の実務家のなじんでいる領域にも応用が急速に進んでいるのである。
ただ、機械学習はこれまで社会調査などで用いられてきた統計学とはかなり毛色が異なり、初学者には少しハードルが高いと感じられる部分があるかもしれない。そこで本特集では、機械学習になじみのない読者も含めて関心を持ってもらえるように、5組の著者たちに、社会学方法論としての機械学習やその応用事例の紹介に加えて、サーベイ調査の自由回答やウェブ調査、因果推論など、社会調査と深く関わる分野で機械学習がどのように役立ちうるかという観点から解説をいただいた。この特集をきっかけにして、社会学や社会調査の領域で機械学習を使ってみたいと思っていただければ幸いである。
瀧川裕貴「特集紹介」から抜粋
2020年に始まったコロナ禍によって、「現場(フィールド)」に出る社会調査の多くは、様々な困難に直面した。だが同時に、社会に広範な影響を与えるコロナ禍のような事象こそ、その影響の範囲や強度を捉えるためにも数々の社会調査を、可能な限りリアルタイムに行う必要があった。それではコロナ禍が始まって早3年、各種形態の社会調査は、どのようにその危機に対応したのか。実際、多くの社会調査が様々な苦難や苦闘を強いられつつも、同時に各種の知見や経験を積み上げてきたのである。
本特集は、コロナ禍に対して様々な社会調査が、どのように実践されている/きたのか、またどのような困難に直面し、どのように変化(もしくは解決)している/きたのか、その記録として意図されたものである。そして結果的に、ただの記録には止まらず、コロナ禍という一つの社会的危機が明らかにした社会調査の問題点を再考し、その解決法、さらには社会調査の「今後」を考えるためのヒントに満ちたものとなった。この特集の内容が現下のコロナ禍への対応のヒントとなるのみならず、将来の「危機」への備えともなれば幸いである。
田辺俊介「特集紹介」から抜粋
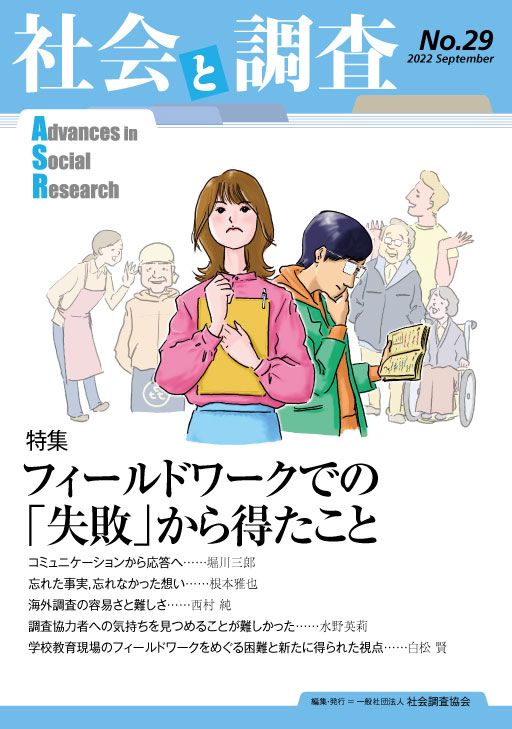
社会と調査 第29号
特集
フィールドワークでの「失敗」から得たこと
- 2022年9月発行
- 編集・発行 社会調査協会
- B5判 108ページ
- 定価 1,200円+税
- ISBN 978-4-903473-99-4
フィールドワークには「失敗」がつきまとう。平たく言えば、「失敗」と感じるのは自分の思うとおりに事が運ばなかったときだろう。とはいえ、未知なるものに出会う、あるいは既知のなかに未知を見出すことが調査なのだから、むしろ想定外の事態は調査を前進させる「チャンス」でもある。
本特集では様々な領域で長年にわたってフィールドワークを行ってきた方々に執筆をお願いし、これまでどのような「失敗」を経験したのか、また、その「失敗」から何を学び、どのように研究を発展させてきた(させようとしている)のか論じていただいた。いずれの論稿も、ただ反省するだけでは不十分であり、とことん「失敗」と向き合い、研究に取り込み、さらにフィールドへと投げ返すことがいかに重要であるのかを教えてくれる。「転んでもただでは起きない」という粘り強さこそが研究を深化させ、さらなる成果を生み出すことにつながる。
普段はなかなか知ることのできない舞台裏を垣間見ることはそれだけで面白く、また勇気づけられる。だが、それは単に調査者のエンパワメントに役立つだけではない。研究領域やフィールドは違っても自分自身の経験と重なるものが多々ある。「裏話」や「失敗談」を共有することは、それぞれの研究の質を高め、学的探求の意義を深めていくことにつながるはずだ。
石川良子「特集紹介」から抜粋
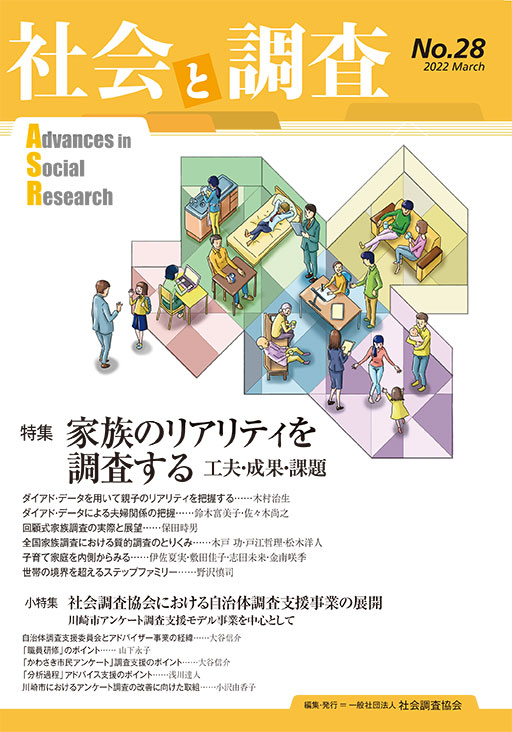
社会と調査 第28号
特集
家族のリアリティを調査する 工夫・成果・課題
- 2022年3月発行
- 編集・発行 社会調査協会
- B5判 122ページ
- 定価 1,200円+税
- ISBN 978-4-903473-98-7
社会調査によって家族のリアリティを把握するには、いくつかの困難が存在する。第1に、同じ行為に対する家族成員間の認知(主観的リアリティ)のズレがある。両者を同時に対象としたダイアド・データの取得は、この問題の1つの解決策となる。第1論 文は親子関係に焦点化したダイアドデータによる研究のレビューと独自の調査プロジェクトの紹介、第2論文は夫婦間での認識のズレに着目した研究例になる。
第2の問題は、刻々と変化する家族の実態や経験をどう捉えるかである。パネル調査という方法もあるが、費用・ケースの脱落・テーマの陳腐化等の欠点がある。第3論文は、これらの欠点を考慮して実施された回顧式質問紙調査の試みである。第4論文では、『全国家族調査(NFRJ)』の回答者を対象とした、家族経験についてのインタビューやフィールドワークのデータを、混合研究法での活用も視野に入れた汎用質的データとしてアーカイブ化する試みを紹介する。第5論文は、4年間にわたり、子育て家族を継続的に観察するという意欲的な調査経験から抽出された、視点と知見の報告になる。
さらに、誰を「家族」に含めるかという問題もある。第6論文では、近年増加する非標準的家族の一例としてステップファミリーに焦点化し、「集団論的家族パラダイム」からの脱却とネットワーク論の有効性を論じている。
荒牧草平・多賀 太「特集紹介」から抜粋
科学的・公的な性格を備える社会調査では、近年その成果の再現可能性が重視されるようになってきている。その背景には、データをオープン化・標準化することによって研究成果の公正で有効な共有の促進をめざす世界的な科学界の潮流が ある。ところで、データが共有されて再現可能性を備えるには、その内容を記述する共通の形式が重要になる。なぜなら、共通の形式で構造や要素が記述されたデータであれば、他者がそれを読み解いて利用することが容易になるからである。そこで注目されるのが、メタデータを含むデータの形式を整理して取りまとめた、データ標準である。医薬品情報や地理情報など、いくつかの学問領域ではデータ標準とその共有が確立しているが、社会調査の分野においてはどうなっているだろうか。
今回の特集では、オープンサイエンスや再現可能性に関する議論の現状を概観したうえで、社会調査の分野における、データ標準を整備しながらデータの共有を進めている事例を紹介する。読者諸氏がこうした内容にふれることにより、社会調査の共有知が発展することを期待するものである。
中野康人「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
賃金格差、ワーキングプア、ハラスメント、やりがい搾取、ワーク・ライフ・バランス等々、働き方をめぐる様々な問題が指摘されている。そうした問題を正確に把握し、実効性のある解決方法を明らかにするためには、舞台となっている企業組織がどのような論理で動いているかを踏まえる必要がある。本特集は、その代表的な方法を紹介しながら、企業組織の調査法について理解を深めることを目的としている。解題を兼ねた総論として、本稿では企業組織を対象とする調査の特徴を整理することにしたい。
池田心豪「はじめに」から抜粋 詳細はこちらから
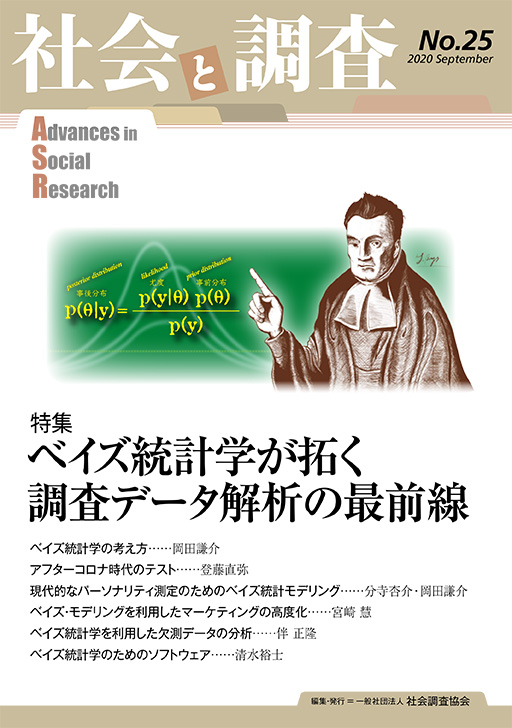
社会と調査 第25号
特集
ベイズ統計学が拓く調査データ解析の最前線
- 2020年9月発行
- 編集・発行 社会調査協会
- B5判 108ページ
- 定価 1,200円+税
- ISBN 978-4-903473-89-5
マイクロソフトの共同創業者であるビル・ゲイツは、1996年にマイクロソフトが競争優位に立っている理由としてベイズ統計学の技術を挙げた。そして、2001年には 21世紀のマイクロソフト社の戦略はベイズ統計学であると宣言した。
現在、ベイズ統 計学は自動運転や迷惑メールフィルターなどで使われ、人工知能開発においても重 要な役割を果たしている。データサイエンスが隆盛を極める現代において、ベイズ 統計学はその中心的存在とも言えるだろう。一方で、ベズ統計学は社会科学分野の調査データ解析研究でも活用されているが、そのことは研究者の中でもあまり知られていない。「ベイズ統計学」という言葉は知っているが、それが一体なんであるかは知らないという読者も多いだろう。
本特集は、心理学・教育学・マーケティング分野でベイズ統計学による研究を行っている6名の執筆者をお招きし、各分野における調査データを題材としてベイズ統計学の活用方法や有効性について論じてもらった。また、ベイズ統計学による分析を具体的に 行いたい読者のために、ソフトウェア案内についても企画した。読者にベイズ統計学への注目を持ってもらい、自身のデータ分析に役立ててもらうことができれば幸いである。
尾崎幸謙「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
日本社会では、国際化の動きのなかで外国にルーツをもつ人々が増えている。児童虐待に巻き込まれる子どもたちも少なくない。日本語能力が十分ではない外国籍の方やそもそも言葉を扱えない乳幼児などのように、自らの意思をうまく伝えることができない人たちが直面する困難を、私たちはどのように捉えればよい のか。
社会調査を行うにしても、自身で調査票に書き込めず、意思表示も難しい当事者の声を聞くことは、どのようにして実現できるのか。意思表示の難しさという点では、少年院在院の非行少年のように接触に制限がありコミュニケーションが取りづらい人々もいれば、被差別地域をとりまく複雑な状況のなかで、自ら口を閉ざす人々もいる。本特集では、こうした人々を対象に社会調査を行ってきた研究者の経験をもとに、社会調査の難しさを強調するだけにとどまらず、どのような工夫が必要であったのかや、得られたデータを分析する際に注意すべき点は何であるかを考えてみたい。
平尾桂子「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
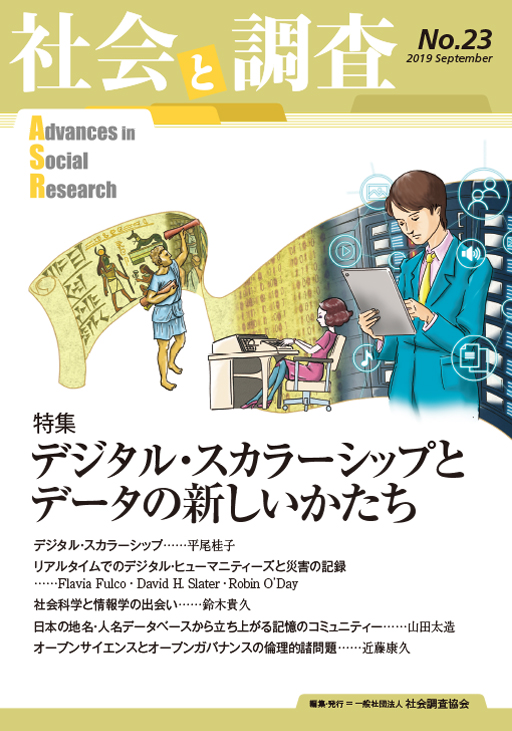
社会と調査 第23号
特集
デジタル・スカラーシップと
データの新しいかたち
- 2019年9月発行
- 編集・発行 社会調査協会
- B5判 113ページ
- 定価 1,200円+税
- SBN 978-4-903473-87-1
「私達、社会調査に携わる者にとって、デジタル技術を用いずに調査データを収集・分析することは考えられない。筆者の専門である社会学を例にとると、「デジタル 社会学」は確かに社会学の下位分野として存在し、その名を冠した書物も多数出版 されているが、それは決して“社会学にデジタル技術を取り入れたもの”ではない。 一方、社会科学よりも格段に長い歴史をもち、紙や羊皮紙に書かれたテキストや絵画などを扱ってきた人文学では、その伝統の深さ故にか、「デジタル・ヒューマニ ティーズ」というように自らの領域に「デジタル」という言葉を冠することに躊躇 しない。
本特集では、人文学の分野から発信されるデジタル・スカラーシップの研究成果を足がかりに、コンピュータ技術によってもたらされる従来の〈人文学〉と〈社会科学〉との対話と交配の可能性、そしてデジタル技術の社会調査への貢献と課題について検討する。本特集を通じて、データや情報の温故知新を堪能していただければ幸いである。
平尾桂子「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
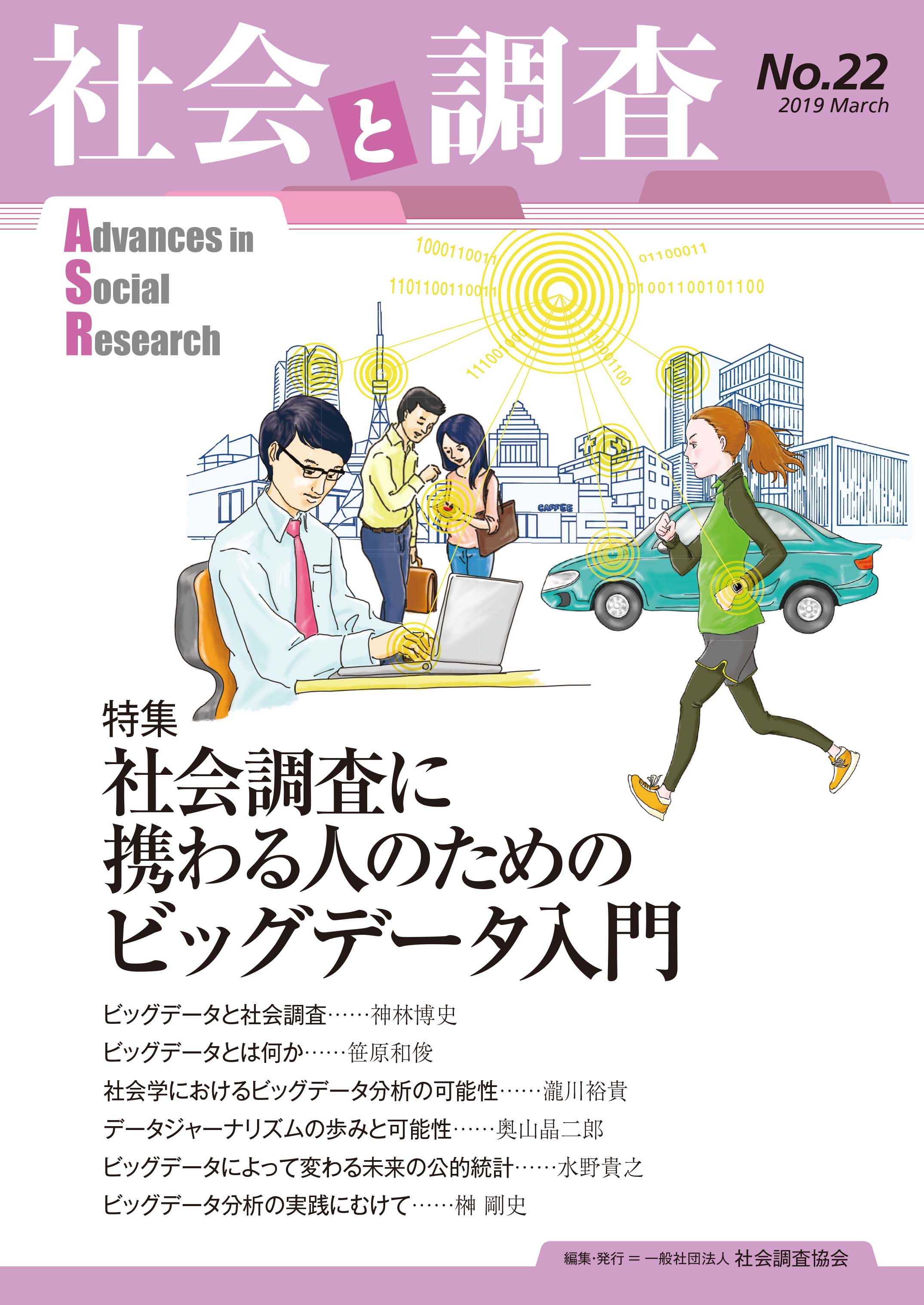
社会と調査 第22号
特集
社会調査に携わる人のための
ビッグデータ入門
- 2019年3月発行
- 編集・発行 社会調査協会
- B5判 133ページ
- 定価 1,200円+税
- ISBN 978-4-903473-86-4
「ビッグデータ」は「AI」と並んで近年の情報技術の発展を象徴する言葉である。ビッグデータに関する解説書をひもとけば、ビッグデータ分析の威力を鮮やかに印象づける事例が綺羅星のごとく並んでいる。しかし社会調査に携わる人(研究・実務で社会調査を実施し、そのデータを利用する人)にとって、ビッグデータは必ずしも身近な存在ではないかもしれない。ビッグデータに積極的に手を出さず、いままで通りの調査・分析を行うぶんにはビッグデータと関わり合うことはまずないからだ。それでは、社会調査とビッグデータの関係はどうなっているのだろう。社会調査を利用する研究領域において、ビッグデータはどのように役に立つのだろうか。
そこで本特集では、「社会調査のことはある程度わかっているけど、ビッグデータのことはよくわからない」という読者を念頭に、ビッグデータとは何か、社会調査を利用する研究・実務領域においてビッグデータがどのように使えるのか・役に立つのかを、5名の専門家に解説していただいた。これまでの『社会と調査』の特集とはやや毛色の異なるテーマであるが、読者のお役にたてば幸いである。
神林博史「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
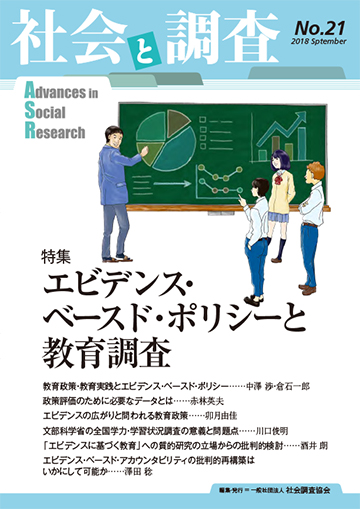
社会と調査 第21号
特集
エビデンス・ベースド・ポリシーと
教育調査
- 2019年3月発行
- 編集・発行 社会調査協会
- B5判 119ページ
- 定価 1,200円+税
- ISBN 978-4-903473-85-7
エビデンスに基づく政策(エビデンス・ベースド・ポリシー)という言葉が、注目を集めている。矢継ぎ早に改革の繰り返されてきた教育現場は疲弊しており、情緒的・感覚的な理由ではなく、客観的かつ科学的な根拠に基づいて政策を実行すべきという声が強まっている。この流れは否定しがたいものであり、客観的かつ科学的なエビデンスを収集する方法として、社会調査が重要性を帯びることに異論はなかろう。
しかしそこで取り上げられるエビデンスとは何か、方法論は確立されているのか、エビデンスの内容に偏りはないのか、エビデンス重視の風潮が教育現場にいかなるインパクトをもたらすのか、といった議論は未だ不十分である。本号の特集では、社会調査を教育政策や教育実践のエビデンスとして活用することについて、様々な観点・立場からの議論を紹介する。今後の教育調査の在 り方を、見つめ直すきっかけとなれば幸いである。
中澤渉・倉石一郎「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
戦後の日本において、早い時期から継続して世論調査を実施してきたのが新聞社、テレビ局などのマスメディアである。そのメディアの調査の手法は、近年大きく変わりつつある。すでに面接調査に代わって電話調査や、郵送法などの自記式調査が活用されるようになっており、最近では電話調査の対象に固定電話だけでなく、携帯電話も加わるようになった。ただ、こうした手法も将来さらに変わる可能性がある。
本特集では、メディアにおいて長く調査に携わってきた5名の方に寄稿をお願いし、メディアが行う調査を「手法の変遷」という観点から論じていただいた。継続性を重視する立場に立てば、調査方法は変えないことが大原則である。だがこれまでの歴史を振り返ると、調査環境やデータへのニーズなどの変化、すなわち社会の変化に応じて調査の手法にも変革が行われた。その中で何が変わり、何が変わらなかったのか―― 今後の調査手法を考えるうえでもあらためて理解しておきたい。
荒牧 央・佐藤 寧「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
社会調査は社会を〈知る〉ための技術として発展を重ねてきた。今日それは高度な専門性を有するひとつの世界を形成している。こうした〈知る〉力をより意味あるものとして社会の中で活かしていくために、いま私たちは何ができるだろうか。
本特集では〈伝える〉こととして社会調査を捉え直してみることを提案したい。様々なオーディエンスと関わり合い、調査の成果を表現し、よりよく伝えていくことは、社会調査の社会的意義や社会的役割という見地からも重要であろう。
第一論文では、社会調査史の源流にある表現への志向を手がかりに「調査と表現」に関する問いの構図を展望する。石倉義博氏・西野淑美氏による第二論文では、学術的知見の提示のあり方や、調査者としての地域への関わり方について論じる。亀井伸孝氏による第三論文では、表現の媒介としての「視覚」に着目し、それを活用することの可能性と諸問題について論じる。青木深氏による第四論文では、調査の成果を「書く」行為に着目し、それが調査者と読者を結ぶ多元的な時間を編成していくさまについて論じる。小倉康嗣氏による第五論文では、社会調査の社会的実践性とその課題を、パフォーマティブな調査表現を試みた経験を踏まえて論じる。
松尾浩一郎「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
調査データを取得するプロセスのデータのことをパラデータ(paradata)と呼ぶ。欧米では、このパラデータを利用して調査を改善するための研究が盛んになってきたが、日本でもパラデータを活用できないのだろうか。
本特集では、パラデータの命名者であるミック・P・クーパー氏に、パラデータの概念の誕生から今日までの発展についてご寄稿頂いた。その上でパラデータに以前から関心をお持ちだった識者の方々に、日本の調査でのパラデータの活用を述べて頂いた。
前田忠彦氏は、調査員がデータを取得するプロセスを記録したデータである訪問記録の分析例を示す。保田時男氏は、自らの分析経験を振り返りつつ、訪問記録分析の意義を自省的に検証する。城川美佳氏は、電話調査におけるパラデータ分析の経験からその利用の意義を述べる。大隅昇他4名の諸氏は、ウェブ調査におけるパラデータの活用方法と課題を論じる。
冒頭の松本論文では、これら5本の論文の理解を促せるように、パラデータの基本概念の概説と日本国内の研究状況についての展望を示している。できれば前から順に6本全ての特集論文をお読み頂き、パラデータの活用についてご考察頂きたい。
松本 渉「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
政策の形成・評価・実践と社会調査をつなぐために、私たちはなにを考えるべきなのか。これが本特集の基本的な問いである。
エビデンス(科学的な根拠)に基づく政策(Evidence-Based Policy)への要請が、近年、高まっている。その実践には政策立案の過程に社会調査を適切に位置づける必要があるだろう。また、調査自体が「つかえる」ものでなければならない。
同時に、調査は、それ自体が社会的な営みであり、そこにかかわる人びとの対話や関係の構築をとおしてさまざまなものを生みだしていく。それが一連の政策過程になんらかの効果をもたらすこともある。ワークショップやアクション・リサーチはその一例だ。
このような観点から、本特集では5名の方に「社会調査と政策のあいだ」について考察していただいた。なお、ここであつかう政策は、国や地方自治体によって立案・実施されるものだけではなく、市民レベルでの取り組みまでふくむ「広義の政策」である。また、調査については、上記の意味での政策の立案や評価などを目的として行うものを想定している。これらの論考をとおして、政策と社会調査をつなぐ条件について考えてみたい。
稲月 正「特集紹介」から抜粋 詳細はこちらから
3.11——すなわち、2011年3月11日の東日本大震災から5年が経過する。災害に関する社会調査は、1995年の阪神・淡路大震災以降、災害研究のみならず幅広い分野で行われるようになった。東日本大震災でも、津波については東北地方と東日本の広い範囲で、原発事故の広域避難・広域支援に関してはさらに広い地域で、多様な手法による社会調査が試みられている。震災という困難に、社会調査はどのように挑んでいるのだろうか。
本特集では、岩手県、宮城県、福島県、新潟県のそれぞれのフィールドで調査を行っている6人の方に執筆をお願いした。震災を扱う調査の調査結果そのものではなく、震災の調査に携わるようになった経緯、調査実施における困難や葛藤、それを乗り越えるための方策など、いわば舞台裏を中心に考察していただいた。これを共有し、震災に関わる社会調査のあり方について検討したい。
阿部晃士「特集紹介」より抜粋詳細はこちらから
社会調査協会のホームページはこちら
第15号までのバックナンバーはこちら
-
新刊
- 晩恋
映子と爺のラブメール - バイオロギング2
動物たちの知られざる世界を探る - 沖縄にそそがれる大御心
-
WAKUWAKUときめきサイエンスシリーズ
- にぎやかな田んぼ
イナゴが跳ね、鳥は舞い、魚の泳ぐ小宇宙 - 海は百面相
- 日本のサル学のあした
霊長類研究という「人間学」の可能性 - 景観の生態史観
攪乱が再生する豊かな大地 - バイオロギング
最新科学で解明する動物生態 -
シリーズ 人と風と景と
- 吉村元男の景といのちの詩
- 「百人百景」京都市岡崎
-
シリーズ 京の庭の巨匠たち
- 重森三玲Ⅱ
自然の石に永遠の生命と美を贈る - 小堀遠州
気品と静寂が貫く綺麗さびの庭 - 植治七代目小川治兵衞
手を加えた自然にこそ自然がある - 重森三玲
永遠のモダンを求めつづけたアヴァンギャルド -
社会と調査
- 社会と調査 第18号
- 社会と調査 第17号
- 社会と調査 第16号
- バックナンバー
-
シリーズ 文明学の挑戦
- 地球時代の文明学2
- 地球時代の文明学
-
その他の本
- 海の姿を測る
海洋計測の原理と進化する技術 - 桜の教科書
サクラを美しくまもる人の智恵と技 - 欝〈うつ〉に離婚に、休職が…
ぼくはそれでも生きるべきなんだ - 人間科学としての地球環境学
人とつながる自然・自然とつながる人 - 改訂 水中音響学
- L'ART CULINAIRE AU JAPON
日本の食文化史 - まねまねヨーガ
子どもとおとなのキレイな姿勢をつくる絵本 - simBio
心筋細胞<Kyotoモデル>の
コンピュータ・シミュレーション - 京都学校物語
- 長崎屋かく子の青春日記
- 京のたつみに住みなれて
- 遙かなり白き姑娘の微笑み
中国四川省の未踏峰四姑娘山初登頂 - どすねん (No.0~7)
-
非売品
- 野村直晴
その夢と精神のたたずまい - 転進、転進50年
- 京のきょう・あすの京
- 笑って振り返りたい